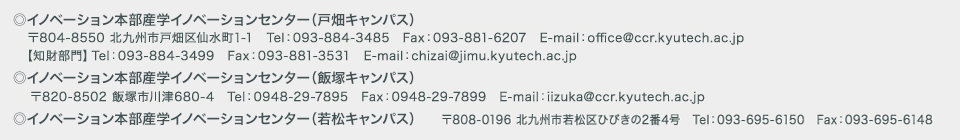教授
もりもと ゆうすけ
子どもの頃から生き物が動いている姿を見るのが好きで、ずっと動いているものの研究を中心におこなっています。機械のように洗練された動きをすることもあれば、わけのわからない適当な動きをすることもある生物たちに魅了されています。
自分の目で生命現象を見る
生物物理学、分子生物学、細胞生物学
蛍光顕微鏡、ライブイメージング、細胞運動、シグナル伝達、モータータンパク質、膜電位、細胞内pH
細胞における電気化学ポテンシャル勾配は、細胞膜内外のイオン濃度差による化学ポテンシャル差と、膜電位による電気ポテンシャル差により形成されます。この電気化学ポテンシャルは、生命にとって必須の共通エネルギーとしてさまざまな生命機能に利用されています。一方、がん細胞や一部の疾患において、細胞内のイオン濃度などが正常な細胞とは異なっていることが知られており、このことが病気を引き起こす一因ではないかと考えられています。
実際の生きた細胞の中でイオンや膜電位がどのように働いているかをライブイメージング技術によって目で見ることができるようにすることにより、電気化学ポテンシャルの生命機能における役割を明確にしようとしています。
1.真核生物のシグナル伝達に関する研究
研究には細胞性粘菌というモデル生物を用いています。細胞性粘菌は特徴的な生活環をもつ真核生物で、通常は単細胞アメーバとして生活していますが、餌が枯渇すると自身が産生するcAMPという物質をシグナルにして集まって多細胞体を形成し、最終的には柄と胞子からなる子実体になります。この生活環の中で見られる走化性運動や細胞分化などの生命現象において、電気化学ポテンシャルがどのように利用されているのかを研究しています。
2.生体分子モーターのエネルギー変換機構に関する研究
バクテリアなどの原核生物がもつ生体分子モーターが、電気化学ポテンシャル勾配をどのように利用しているかについての研究も行なっています。
全自動蛍光顕微鏡
蛍光分光光度計
プレートリーダー
【共同研究】
・細胞性粘菌のシグナル伝達機構の研究(大阪大学大学院生命機能研究科 上田昌宏教授)
・バクテリアべん毛タンパク質輸送装置の研究(大阪大学大学院生命機能研究科 南野徹准教授)
・バクテリアべん毛モーターの研究(東北大学大学院工学研究科 中村修一准教授)
【主な論文】
Minamino, T., Morimoto, Y.V., Kinoshita, M. & Namba, K. Membrane voltage-dependent activation mechanism of the bacterial flagellar protein export apparatus. Proc Natl Acad Sci U S A 118, e2026587118 (2021).
Morimoto, Y.V., Namba, K. & Minamino, T. GFP fusion to the N-terminus of MotB affects the proton channel activity of the bacterial flagellar motor in Salmonella. Biomolecules 10, 1255 (2020).
Suzuki, Y., Morimoto, Y.V. et al. Effect of the MotA(M206I) mutation on torque generation and stator assembly in the Salmonella H+-driven flagellar motor. J Bacteriol, e00727-00718 (2019).
Hashimura, H., Morimoto, Y.V., Yasui, M. & Ueda, M. Collective cell migration of Dictyostelium without cAMP oscillations at multicellular stages. Commun Biol 2, 34 (2019).
Morimoto, Y.V. et al. High-resolution pH imaging of living bacterial cells to detect local pH differences. mBio 7, e01911-01916 (2016).
Morimoto, Y.V. & Minamino, T. Structure and function of the bi-directional bacterial flagellar motor. Biomolecules 4, 217-234 (2014).