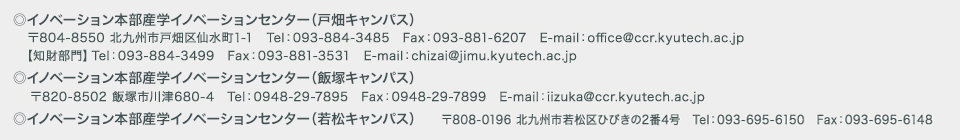准教授
こうの はるひこ
大学時代に、慶應義塾大学の棚橋隆彦教授(現名誉教授)の下で数値流体力学の研究に取り組みました。シミュレーションを主体とする研究では物理現象の深い洞察と適切な離散化手法、そして高度な数学力を要します。核融合プラズマや移動界面を有する電磁流体が内包する複合的な物理現象に対し、それらに隠された真実の一端を理論とシミュレーションで垣間見ることができたときの喜びが、自己の未熟さと闘いながら日々研鑽を積む原動力になっています。
電磁場との相互作用に隠された物理を解き明かす
プラズマ科学、核融合学、流体工学
磁場核融合、電磁流体、界面、有限要素法、数値流体力学
【核融合炉壁におけるシースとプラズマ波の相互作用】(最終更新日:2013年10月4日)
私がこれまで取り組んできた研究分野は、数値流体力学、電磁流体の理論、応用数学、プラズマ物理、計算化学と多岐に渡りますが、ここでは核融合におけるプラズマ物理の研究例をご紹介いたします。
核融合発電は世界的に増加を続けるエネルギー需要を永続的に満たす可能性を秘めており、その実現に向けて現在フランスのカダラッシュにおいてITER(国際熱核融合実験炉)の建設が国際的な協力の下で進められています。核融合発電では、異なる水素の同位体の原子核同士が衝突して核融合反応を起こすときに生じるエネルギーを利用するため、水素原子中の原子核と電子が分離するような超高温のガス状態、すなわちプラズマを保つ必要があります。現在の主なトカマク型核融合炉では、その中心イオン温度を1億度以上にまで上げて運転を行っています。
上記の温度までプラズマを加熱する方法はいくつか挙げられますが、私の研究ではイオンサイクロトロン加熱に着目しています。これは電子レンジのマイクロ波加熱と同じ原理で、イオンサイクロトロン波と呼ばれる波動をトカマク断面の中心に近い領域で共鳴吸収させて、プラズマを核融合反応に必要な温度まで加熱する方法です。トカマク型核融合炉の実験において数十年に渡って使用され、その技術は大きく向上しましたが、課題も多く発見されました。その1つが、本研究のテーマであるRF(radio-frequency)シースの問題です。
トカマク断面の中心から離れたスクレイプオフ層と呼ばれる領域では、磁力線の両端が壁面と接しています。プラズマを構成する荷電粒子は主に磁力線に沿って運動しますが、電子の質量はイオンの質量と比較してずっと小さいため、電子の方がより速く金属壁へ逃げていきます。その結果、プラズマが電気的に中性な状態を保つように、壁面においてシースと呼ばれるポテンシャル障壁が生じます。それに加えて、イオンサイクロトロン加熱では大きな電場を伴ったプラズマ波(速波と低速波)が壁面に到達するため、壁面近傍の電子がさらに加速され、シース内のポテンシャル障壁の時間平均はプラズマ波が存在しない場合と比べてより高くなります。重要な点は、増加したシース電圧によって大きな質量を有するイオンが壁面に向かって加速され、壁面との衝突により不純物がプラズマ中に混入することです。このスパッタリングと呼ばれる問題により高温のプラズマが冷却され、核融合反応の効率が大きく低下することが確かめられています。
本研究では、トカマクポロイダル面におけるプラズマ波とRFシースの非線形相互作用を計算しうる大規模並列有限要素解析スキームを開発し、様々な条件におけるシース電圧の特性を明らかにすることを目的としています。現象を解析する上で困難な点の1つはプラズマ波の波長とシース幅のスケールが大きく異なることですが、本手法ではシース内部の物理を適切に近似することで、それを境界条件として解析モデルに取り込んでいます。図1は、上下方向に周期性を仮定したスラブモデルにおいて計算されたシースプラズマ波の挙動を表しています(詳細はKohno et al., Phys. Plasmas, 19, 012508 (2012)参照のこと)。これはプラズマ中では減衰する波動がシースとの相互作用によって壁面に沿って伝播する波動に変換される面白い現象を示しています。また、シースに沿って背景磁場のこう配がある条件を満たした形で変化する場合、図2に示すようにシースに沿う波動エネルギーが局所的に蓄積されることを数値解析と理論解析の両面で明らかにしました(詳細はKohno et al., Phys. Plasmas, 20, 082514 (2013)参照のこと)。これらはアメリカの研究者と共同で行った研究の成果ですが、未解明な部分が多く残されているエッジプラズマ領域の物理の一部を解明することを目指して現在も解析を進めています。
図1 シースプラズマ波の挙動
(シースを右側境界に配置、黒い斜線は磁力線を表している)
図2 シース上における波動エネルギーの蓄積
(灰色と黒の曲線は、それぞれシース境界条件と導体壁境界条件を課した場合に対応)
・磁場核融合におけるRFシースの数値解析
・自由表面の変形を考慮した電磁流体流れの数値解析
・交流磁場下における電磁流体流れの3次元数値解析
【共同研究者】
Klaus-Jürgen Bathe (MIT, USA)
Sergei Molokov (Coventry University, UK)
James R. Myra, Daniel A. D’Ippolito (Lodestar Research Corporation, USA)
『気泡又は介在物もしくは双方の除去方法』
特許第6948691号 河野 晴彦、岩永 貴裕
https://patentfield.com/patents/JP2017092912A
『気泡又は介在物もしくは双方の除去装置及び除去方法』
特許第7573263号 河野 晴彦
https://patentfield.com/patents/JP2020150503A#/
(いずれも、主に連続鋳造工程において、鋳型内部の溶鋼に混入される微細な気泡や介在物を効果的に取り除くことが可能な技術です。これにより、鋼片の内部欠陥の低減効果が期待できます。)
・詳解 流れの数値計算 -有限要素法による非圧縮性流体解析の基礎- 【コロナ社】(2022)
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339046762/
【主要論文】
(1) 木下 健生,河野 晴彦,「1次元領域で3節点要素を用いる有限要素法の一考察」,日本計算工学会論文集,2025年7月,20250007.
(2) H. Kohno, J. R. Myra, "Investigation of two-dimensional radio-frequency sheath properties using a microscale fluid model," Nuclear Fusion, 2025, Vol. 65, 026012.
(3) H. Kohno, J. R. Myra, "A finite element procedure for time-dependent radio-frequency sheaths based on a two-dimensional microscale fluid model," Computer Physics Communications, 2023, Vol. 291, 108841.
(4) 久米川 知也,牟禮 良晃,河野 晴彦,「交流磁場下の3次元電磁流体流れにおける連成解析手法の検討」,日本計算工学会論文集,2022年10月,20220016.
(5) Haruhiko Kohno, "Convergence improvement of the simultaneous relaxation method used in the finite element analysis of incompressible fluid flows," Engineering Computations, 2020, Vol. 37 No. 2, pp. 481-500.
(6) J. R. Myra, H. Kohno, “Calculation of RF sheath properties from surface wave-fields: a post-processing method,” Plasma Physics and Controlled Fusion, 2019, Vol. 61, 095003.
(7) J. R. Myra, H. Kohno, “Radio frequency wave interactions with a plasma sheath: The role of wave and plasma sheath impedances,” Physics of Plasmas, 2019, Vol. 26, 052503.
注目に値する論文の一つとして、Physics of Plasmasの"Editor's Pick"に選出されました。(本学公式ウェブサイトの掲載記事はこちら)
(8) H. Kohno, J. R. Myra, “Radio-frequency wave interactions with a plasma sheath in oblique-angle magnetic fields using a sheath impedance model,” Physics of Plasmas, 2019, Vol. 26, 022507.
(9) 牟禮 良晃,河野 晴彦,「交流磁場下における導体壁に囲まれた電磁流体流れの3次元数値解析」,日本機械学会論文集,2018年7月,84巻863号,17-00589.
(10) H. Kohno, J. R. Myra, “A finite element procedure for radio-frequency sheath-plasma interactions based on a sheath impedance model,” Computer Physics Communications, 2017, Vol. 220, pp. 129-142.
(11) Haruhiko Kohno, “A mixed-interpolation finite element method for incompressible thermal flows of electrically conducting fluids,” International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2017, Vol. 83, pp. 813-840.
(12) H. Kohno, J. R. Myra, D. A. D’Ippolito, “Numerical investigation of fast-wave propagation and radio-frequency sheath interaction with a shaped tokamak wall,” Physics of Plasmas, 2015, Vol. 22, 072504; Physics of Plasmas, 2016, Vol. 23, 089901 (erratum).
(13) Haruhiko Kohno, “An efficient, high-order finite element method using the nodal averaging technique for incompressible fluid flows,” Computer Physics Communications, 2015, Vol. 195, pp. 68-76.
(14) H. Kohno, J. R. Myra, D. A. D’Ippolito, “Radio-frequency sheath-plasma interactions with magnetic field tangency points along the sheath surface,” Physics of Plasmas, 2013, Vol. 20, 082514.
(15) Haruhiko Kohno, Jean-Christophe Nave, “A new method for the level set equation using a hierarchical-gradient truncation and remapping technique,” Computer Physics Communications, 2013, Vol. 184, pp. 1547-1554.
(16) H. Kohno, J. R. Myra, D. A. D’Ippolito, “A finite element procedure for radio-frequency sheath-plasma interactions in the ion cyclotron range of frequencies,” Computer Physics Communications, 2012, Vol. 183, pp. 2116-2127.
(17) H. Kohno, J. R. Myra, D. A. D’Ippolito, “Numerical analysis of radio-frequency sheath-plasma interactions in the ion cyclotron range of frequencies,” Physics of Plasmas, 2012, Vol. 19, 012508.
(18) Haruhiko Kohno, Klaus-Jürgen Bathe, John C. Wright, “A finite element procedure for multiscale wave equations with application to plasma waves,” Computers & Structures, 2010, Vol. 88, pp. 87-94.
(19) H. Kohno, S. Molokov, “Interfacial instability in aluminium reduction cells in a vertical magnetic field with a transverse gradient to the sidewall,” Physics Letters A, 2007, Vol. 366, pp. 600-605.
(20) Haruhiko Kohno, Sergei Molokov, “Finite element analysis of interfacial instability in aluminium reduction cells in a uniform, vertical magnetic field,” International Journal of Engineering Science, 2007, Vol. 45, pp. 644-659.
(21) Haruhiko Kohno, Klaus-Jürgen Bathe, “A nine-node quadrilateral FCBI element for incompressible fluid flows,” Communications in Numerical Methods in Engineering, 2006, Vol. 22, pp. 917-931.
(22) Haruhiko Kohno, Klaus-Jürgen Bathe, “A flow-condition-based interpolation finite element procedure for triangular grids,” International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2006, Vol. 51, pp. 673-699.
(23) Haruhiko Kohno, Klaus-Jürgen Bathe, “Insight into the flow-condition-based interpolation finite element approach: solution of steady-state advection-diffusion problems,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2005, Vol. 63, pp. 197-217.
(24) Haruhiko Kohno, Takahiko Tanahashi, “An application of GSMAC-FEM to coupled natural and Marangoni convection in a square cavity,” International Journal of Computational Fluid Dynamics, 2005, Vol. 19, pp. 329-335.
(25) Haruhiko Kohno, Takahiko Tanahashi, “Numerical analysis of thermal melt flow and melt/solid interface shapes in the floating zone method,” International Journal of Computational Fluid Dynamics, 2005, Vol. 19, pp. 243-251.
(26) Haruhiko Kohno, Takahiko Tanahashi, “Numerical analysis of deformed free surface under AC magnetic fields,” International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2004, Vol. 46, pp. 1155-1168.
(27) Haruhiko Kohno, Takahiko Tanahashi, “Numerical analysis of moving interfaces using a level set method coupled with adaptive mesh refinement,” International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2004, Vol. 45, pp. 921-944.
(28) 河野 晴彦,棚橋 隆彦,「微小重力場におけるFZ法単結晶成長問題(第2報,コイルの位置・巻き数,および表面張力に依存する液柱変形挙動)」,日本機械学会論文集(B編),2003年8月,69巻684号,pp. 1746-1753.
(29) H. Kohno, T. Tanahashi, “Three-dimensional GSMAC-FEM simulations of the deformation process and the flow structure in the floating zone method,” Journal of Crystal Growth, 2002, Vol. 237-239, pp. 1870-1875.
(30) 河野 晴彦,棚橋 隆彦,「GSMAC-FEMによる大口径CZ法融液内の熱流動のLES解析」,日本機械学会論文集(B編),2002年4月,68巻668号,pp. 1044-1051.
(31) 河野 晴彦,棚橋 隆彦,「微小重力場におけるFZ法単結晶成長問題(自由表面にLSMを適用したHybrid FEM-BEMによる3次元流動解析)」,日本機械学会論文集(B編),2001年6月,67巻658号,pp. 1408-1415.
❖ researchmapの紹介ページ
https://researchmap.jp/haruhiko_kohno/
❖ 夢ナビ講義
https://douga.yumenavi.info/Lecture/PublishDetail/2019552710?back=
❖ 詳しい研究者情報
https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/100000658_ja.html