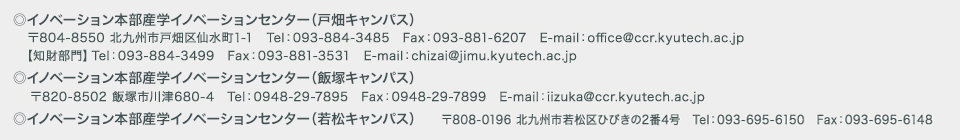准教授
おおやま たかとし
高校までを過ごした長崎県では「平和教育」が行われていました。原爆被爆の悲惨さを学ぶとともに、戦争の愚かさを再認識する機会となっていました。他方で、9.11同時多発テロ事件やイラク戦争が勃発した頃から、テレビでは「平和」のための自衛隊海外派遣が語られるようになりました。これら2つのもっともらしい語り口に向き合うなかで、言葉と政治の問題について関心を持つようになりました。
戦後日本の「平和主義」はどのように揺らいできたのだろうか
国際関係論、政治学、社会学
自衛隊海外派遣、政府開発援助(ODA)、平和主義、国際貢献、日米同盟、国益
日本では第二次世界大戦での敗戦を受け、戦後長らく「平和主義」を対外政策の柱として掲げてきました。高度経済成長を遂げて「経済大国」となってからも、政府開発援助(ODA)を通してアジア諸国との協力を深め、自衛隊の海外派遣には自制をかけてきました。しかし、冷戦が終わってバブル経済が弾けたころから、日本社会のあり方に変化が見られるようになります。自衛隊の海外派遣は日本の対外政策のひとつの手段として認知されるようになり、多額のODAを拠出することに対しても反対意見が表出するようになったのです。現在では、戦後の日本社会に根づいてきた「平和主義」の揺らぎが意識されるようになっています。
とはいえ、長らく根づいてきた社会的な意識は、なぜ、どのようにして揺らいだのでしょうか。また、曖昧模糊とした社会的な意識なるものをどのようにして捉えたらいいのでしょうか。これまでの私の研究では、日本の国際平和協力(自衛隊海外派遣と開発協力政策)をめぐって国会や新聞、論壇誌などで繰り広げられた政治コミュニケーションを視野に入れ、これらの議論を方向づけたキーワード(たとえば、「国際貢献」や「国益」など)の変遷に注目した歴史的な考察を行ってきました。これにより、日本の対外政策をめぐる知的フレームワークの変遷が時代背景とともに詳らかになり、これと連動した形で政局も動いていた様子を描き出すことができました。
このような研究を踏まえつつ、近年は日本の国際平和協力が現地社会の側でどのように捉えられているのかを明らかにする共同研究も進めています。国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の一員としての自衛隊の活動(1992~93年)を例として、派遣された自衛官や宿営地周辺の住民、カンボジアの省庁関係者などに幅広くインタビューを行ってきました。自衛隊の宿営地が設置された土地をめぐる紛争であったり、男女ないし地域ごとの反応の違いであったり、日本のなかでは意識されることのなかった自衛隊海外派遣の影響について考える手がかりが得られつつあります。
これらの研究から日本の国際平和協力をめぐる自己認識/他己認識の変遷を明らかにすることで、「平和主義」の揺らぎの実相に迫ろうとしているところです。
【共同研究】
・「日本の国際平和協力は現地社会でどのように受け止められているのだろうか:自衛隊カンボジア派遣をめぐる人類学的調査を糸口に」公益財団法人村田学術振興財団:研究助成(人文)、2019年7月-2021年3月(研究代表者)
【受託研究】
・「日本の開発協力の歴史」独立行政法人 JICA研究所、2016年10月-2017年12月(研究分担者)
【論文】
・ 大山貴稔(2019)「戦後日本におけるODA言説の転換過程:利己主義的な見地は如何にして前景化してきたか」JICA研究所編『「日本の開発協力の歴史」バックグラウンド・ペーパー』No.8、1-24頁。
・大山貴稔(2018)「戦後日本における「国益」概念の淵源:“national interest”をめぐる翻訳論的考察」国際安全保障学会編『国際安全保障』第46巻第3号、113-131頁。
など