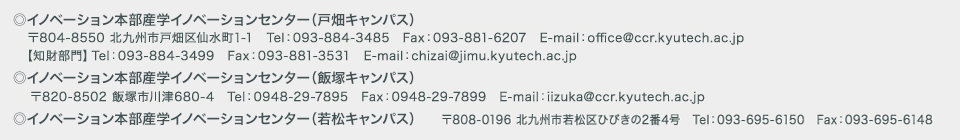准教授
いぐち なおき
日本でずっと育ったわけではなかった私にとって、日本の慣行や文化は必ずしもなじみやすいものではありませんでした。そんな中、社会で当たり前とされていることを相対化し、その変化の可能性までを議論できる社会学に魅力を感じました。特に自分の周りでも多くの学生が疲弊していた就職活動について、何が起きていて、その原因は何かを問うようになりました。
日本の労働や雇用をめぐる文化を
相対化し、新しいあり方を考える
社会学
就職、採用、人事管理、キャリア、転職、資本主義
かつて日本で典型的とされてきた、「立派な企業に長年勤め続けるのが立派な生き方だ」という考えやそれを元に設計された制度が、必ずしも現在の多様な人々のキャリアの希望とあわなくなっているのではないか、という問題関心のもと、主に3つのプロジェクトを進めています。
第1に、日本の大学生の就職・採用活動について、なぜ負担感や不満が生じるのかをインタビュー調査を通じ探ってきました。結果として、会社への志望度や従順さを求める選考が、学生にとって必ずしも合理的ととらえられず、それが会社への志望度の低下や就活そのものへの意欲低下に結びつく場合もあることが分かってきました。
第2に、ビジネス的手法を用いて社会問題を解決する社会的企業について、従業員がいかにしてそこで働くようになったのか、を、韓国のそれと比較しながら研究しています。結果、日本で社会的企業に入職するのは必ずしも特殊な経歴や意識を有する人というわけではなく、新卒時は一般営利企業で働いていた人も多いことが分かりました。一方で、単に自社の利益だけを目指すのではなく、受け手や社会全体の利益を目指し働けることや、仕事の裁量が大きいことなど、独自の働き方の魅力があることが明らかになりました。
第3に、転職についての若年者の意識の変化について、量的データを基に、アメリカや韓国と比較しながら探っています。日本では転職というと自己実現を目指すものというイメージも強いですが、家庭の都合やステップアップのために柔軟にするあり方も他国では多くみられます。これらのあり方が広まっていくのか、それがしやすい条件は何なのか、を探っています。
これまで就職活動や転職など個別具体的な局面にフォーカスして、日本の雇用・働き方の特徴を探ってきましたが、アメリカなど他国との比較のもと、それらの背景にある人々の価値観やその歴史的起源も探ってみたいです。
【共同研究】
『社会的企業の生態系における組織の持続性と担い手のキャリアの経済社会学的研究』(トヨタ財団,D18-R-0122, 2018-2022)(研究分担者)
『社会的企業エコシステムの比較社会学的研究:東京・ソウル・シンガポールを対象に』(科研費,24K00332, 2024-)(研究分担者)
【著書】
『選ぶ就活生、選ばれる企業――就職活動における批判と選択』晃洋書房,2022年(単著)
『社会的企業の日韓比較――政策・ネットワーク・キャリア形成』明石書店,2024年(分担執筆)