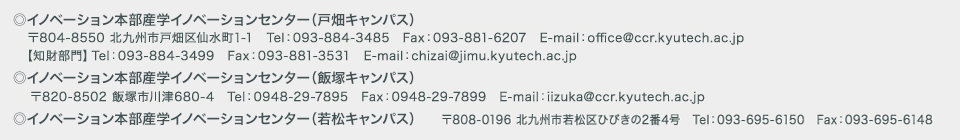まさか!の時に役立つ安全・安心な地盤の研究
地盤工学
地盤防災、地震土砂災害、建物基礎
構造物(建物、道路、ダム、橋など)や都市は、自然あるいは人工の地盤によって支えられています。地盤は、地震や水害などの影響を受けて大きく変形、変化して災害被害を大きくします。地震や水害の多いわが国は、「砂上の楼閣」のように一瞬にして全てを失うリスクが高く、この影響をいかに軽減するかを研究し、安全で安心な生活環境を保持することを研究しています。地盤工学は20世紀後半に鉄、コンクリート、プラスチックなどの材料を使用することやコンピューターによる解析などによって大きく進化し様々な工法を提供してきました。また人間が発生させた廃棄物の処理は危険な核廃棄物を初めとして、生活廃材のゴミや焼却灰など様々ですが、これをいかに安定した地盤の上で保持し、利用するかは私たちの子孫に果たすべき責任と言えます。地盤工学は土木工学のひとつですが、環境問題にも対応できる優れた科学、学問です。福岡西方沖地震など国内の災害時には現地調査を行い理論と実証を行ってきましたが、次の世代へ向けての地盤工学の進化に取り組んでいきたいと思います。
地盤防災の視点から環境への影響を研究していきたいと考えています。
地震や水害などで変化した地盤によって、それまでの環境が悪化することも予想されます。廃棄物処理、既設の構造物の補修強化、新たに人工地盤を造る時などに環境負荷を与えない手法も考えたいと思っています。
① 遠心模型実験装置(Centrifuge)
② 振動台(Shaking Table)
▶3号地嵩上堤体地震時の安定検討外 (2007)
▶テールアルメ工法の橋台背面補強への応用実験 (2007)