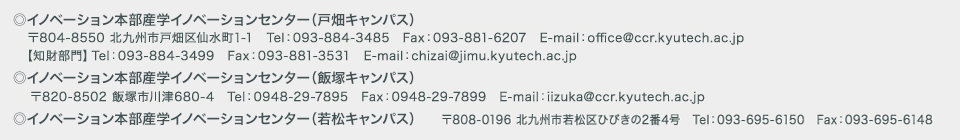教授
わがつま ひろあき
SF映画に登場する人に冗談を言うコミカルな人工知能や雰囲気を察してさりげなく人を助けるロボットが現実にあったら面白いと思い、コンピュータ開発エンジニアを辞め、脳の神経回路網の研究を始めました。現在は機構設計から考えるロボットではなく、ニーズとしての人間親和性に注目してロボットの「脳」を研究しています。
情動とリズム協調の原理から人と共感する社会脳ロボットの開発を
ソフトコンピューティング・生体生命情報学・知能ロボット
ニューロコンピューティング・Brain-IS・脳型知能
当研究室では、Brain-IS(Brain-Inspired Systems・脳型知能創発システム)エンジニアを育成する教育プログラムとして,ものづくり技術からチームマネージメント能力を備える実践的エンジニア技術を身につけて研究を進めます。年功序列でなく、一人一人が責任を持って研究プロジェクトを進めるため、先輩や教員を含めたフラットチームを編成し各々リーダーとして指揮することで、「主体性」「コミュニケーション能力」「実行力」など企業が必要とする三大要素を鍛えます。
研究テーマは「既存技術で何かできるか」というシーズ中心でなく「社会に何が必要で、そのための総合技術をどう創出するか」のニーズに注目して、研究を進めます。脳型ロボット工学では、事故や病気で脳に障害を持った方などに必要な支援をするロボット設計を機構設計/電子回路/脳型理論を総動員して行います。映画「ターミネーター」のように人が恐れるロボットではなく、阿吽の呼吸で、かゆいところに手が届く支援装置を、小さなものから大きなものまで開発できる共通基盤化を行っています。特に、脳の情動回路やリズム協調の原理から人と共感する社会脳ロボットの開発を、脳神経系の生理学者やリハビリテーションの理学療法の専門家と一緒に共同研究しながら進めています。来年度は、キッチンやリビングルームなど家庭環境で人間と共同作業できるロボット製作を進め、ロボカップ@ホームへの参加を検討しています。知能ロボットや特殊機構を持ったロボット設計に興味がある人はどうぞお問い合わせ下さい。
共感型ロボットの家庭環境での実用、ニューロリハビリテーション支援装置の事業化
リアルタイム遠隔ロボット制御装置、
脳機能障害リハビリテーション支援装置
ニューロインフォマティクス(脳情報工学+データベース情報技術)

ヒト型ロボットPLENによるロボット実験